写真:前澤秀登
お気づきになった話
佐々木敦
「お気づきだっただろうか?」ーーこれが彼等が一年間続くという連続イベント「怪物さんと退屈くんの12ヶ月」の第一回に選んだタイトルである。
2014年1月23日木曜日の夜、私は六本木のスーパーデラックスへと足を運んだ。開演15分ほど前に辿り着くと会場は八割方埋まっていた。スーパーデラックスは基本的にコンクリート打ちっぱなしのフラットな空間だが、スペース中央にドラムセットを始め楽器が並べられてあり、その周囲を客席が取り巻いている。私はステージに向かって左側の壁際の席についた。もうそこぐらいしか空いていなかったのだ。ここに座ると、ステージを横向きに挟んでちょうど反対側の、こちらと同様に並べられた席に居る観客たちと向い合う形になる。向こう側もまだ少し空席があるようだ。私は視力の関係で右からの方が見やすいので、移動しようかなとも思ったが、やめにした。ここへ来ると必ず注文する美味しい地ビールを呑みつつ、演奏が始まるのを待つ。
*******
ほぼ毎日、一日一度は新刊棚を覗く書店がある。駅前の中型店舗ということもあり、いつの時間に行っても、それなりに客が居るのだが、新刊といっても私の場合、ほとんどありとあらゆるコーナーをチェックしているので、日によって時間はまちまちだが、暫し店内をうろつくことになる。発売を心待ちにしている本があったりする場合だけでなく、特に探している書籍がなくても、ついつい入ってうろうろしてしまう。要するに習慣に、それも長年の習慣なっているわけだ。そんなある日、ちょっと面白いことに気づいた。
こうしたある程度の規模の店舗には、大抵の場合、いわゆる万引きGメンというか、覆面ガードマンのような人が配置されている。彼ら彼女らは一般客のフリをしながら店内をそれとなく巡回し、あやしい行動を取っている者を発見するや、ひそかに尾行を続け、もしも支払い前の本を持ったまま店を出ようとしたら、そこで声を掛けて事務所への任意同行を求める。私はかなり昔のことになるが、そうした覆面ガードマンに万引き犯と間違えられて店の前でコートのポケットを探られたことがあり、その時の怒りと羞恥の経験により、それほど大型の店ではなくても、そういう人員が客にまぎれて目を光らせていることを身を以て知っていた。そして私は、ある日、そんなガードマンのひとりを発見した、と思ったのである。
彼女の存在に気づいたのは、他でもない、私があまりにもしょっちゅう、その店に通っていたからである。あるとき、中肉中背で、ごく地味な顔立ちにごく地味な身なりの、さほど若くはないがおばさんと呼ばれるにはまだかなり早かろうひとりの女性が、ふと目に留まった。あれ、このひと、前にも見たことがあるぞ。それはしかし、特に訝しむことではない。同じ店によく来ている客は、自分の他にも当然大勢居るわけであり、彼女もその内のひとりに過ぎず、たまたま自分の無意識的な視覚的記憶にいつしか映り込んでいたのが、何かしらの脳内の振る舞いによって、いま突然、ふと認知された、ということなのだろうと、最初は思った。美人とはお世辞にも言えないような、特に目を惹くところのない女性である。しかし確かに、彼女には見覚えがあった。
そのときは、たぶん常連客なのだろうな、などといったことを、これも半ば無意識に思ったとか、そういうことであったと思う。だがしかし、一度認知してしまうと、彼女は非常にしばしば、というよりも、ほぼ必ずと言っていいほど、その店の中で目撃されるようになったのである。雑誌コーナーに居ることは滅多になくて(といっても私があまり雑誌棚には行かないので、実際のところはよくわからないと思ったのだが)、大概はさまざまなジャンルの単行本が置かれているコーナーの隅に立って、静かに、だが熱心に立ち読みをしている。日本文学の場合もあれば、エッセイの棚の場合もあれば、美術書のこともあれば、理系の本が並ぶコーナーでも、思想・人文の一角でも、彼女は発見された。幾人かの客の中に見受けられることもあれば、午前の人気のまだあまりない時間に、他には誰も居ない書棚の陰にひとり佇んでいたこともあった。いつ見ても、棚から取ったであろう一冊の本を開いて読みふける姿が、私の視界の中に飛び込んできた。ほんとうにそれは度々のことであって、私はほとんど、彼女はその書店に住んでいるのではないかとさえ思ってしまうほどだった。
事の次第に気づいたきっかけは、他でもない、この「彼女はその書店に住んでいるのではないか」という奇妙な疑念だった。そして気づいてしまえば推理は早かった。ああ、もしかしてあのひとは覆面ガードマンなのじゃないだろうか。そう考えてみれば全てが氷解する気がした。彼女はいつも、店内でも、あまり多くの客が立ち寄らないような、私ぐらいしか頻繁には行かないようなコーナーにいる。そしていつも目立たぬ感じで、そっと立ち読みをしている。それはつまり死角に控えているということである。そこは万引きには格好の場所であり、それゆえに彼女は、犯罪を見張っているというだけでなく未然に防ぐという意味も込めて、仕事として、そこに居るのではあるまいか。彼女は警備会社に雇われた私服ガードマンなのだ。だからあれほど、いつ私が行っても、あの店に彼女の姿が見つけられるのだ。
この推理は、思いがけないところで裏付けられた。同じ駅に、もう一軒、新しく書店が開店した。私は自宅の最寄り駅から仕事場のあるこの駅に毎日電車で通ってくるのだが、ある日、いつもの習慣をふと変えて、その新しい店に寄ってみることにしたのだ、駅から出て、いつもの書店を通り過ぎ、暫く歩いた先に、その新しい店はある。私は入って、はじめての店内に戸惑いながらも、本好きの習性ゆえ少しわくわくしながら各コーナーを散策した。そして店の奥の方の、私の本もあったりする文芸評論の棚のところまで来て、彼女を発見した。彼女はいつもの店と同じように、黙々と立ち読みをしていた。私は思わず、小さく、お、と声を出してしまいそうになった。いや、それは実際聞こえていただろうと思う。だが彼女は顔を上げることもなく、ただ静かに立っていた。だが私はそのとき、ああやっぱり、これで証明された、という思いだった。彼女が勤める警備会社が、この店も担当しているのだろう。彼女は、おそらく他にも何人かいるのだろう人員と共に、この駅の書店を巡回しているのだ。
そして実際、それから私が二店をほぼ交互にひやかすようになると(もちろん買ってもいたが)、彼女はどちらの店内でも見つけられるようになった。そして私は、ちょっと面白くなってきたのだ。だってこれはあまりにもあからさまな、バレバレの警備とは言えまいか。自分ほどに足繁く同じ書店に通う者が他にどれだけいるかはわからないが(たぶんそんなに多くはあるまいが)、それでもさすがに、あんなにいつ行っても目の前に居るのでは、いつか誰かに気づかれる、いや、もうとっくに気づかれてしまっているのではないか。私と同じように、彼女の存在、いや、遍在に気づいていながら、そして私と同じ結論に達していながら、何喰わぬ顔で、彼女の立ち読み姿をやり過ごしているひとが、結構いたりするのではないだろうか。そう考えてみると、なんだか少し愉快な、痛快な気さえしてきたのである。
親しみが沸いた、というのとはさすがに違うのだが、しかし私は、それから彼女を以前にも増して意識するようになった。そして実際、彼女はますます、本屋の片隅で発見されるようになっていったのである。そもそも向こうは、こちらに気づいているのだろうか。なにしろガードマンなのだから、気づいていない筈がない。立場を裏返せば、私だって異常なほど頻繁にその店に行っているのだから。だが私がやたらとうろうろしているのに対して、彼女は店内の死角とも言える場所にじっと控えている。どういうことなのか見当がついたとはいえ、実に変な感じである。というよりも、これはある意味、もはや警備の機能を果たしてはいないのではあるまいか。気づいてみれば、私が彼女に気づいてから、すでに数ヶ月が過ぎようとしている。だがそれでも彼女は変わりなく、私がその店に行けば、そこに居る。これはさすがに担当を変えるべきではないだろうか。私はまったく無関係なのに妙な心配をしてしまい、そんな自分に内心笑ってしまうこともあった。
そこで私は、ささやかな妄想を抱くようになったのだ。彼女に声を掛けてみたらどうなるのだろうかと。彼女は、自分の存在が、その役目が、他の客には気づかれていないと思っている。少なくとも、そういうことになっていないと、あの仕事は続けられまい。あるいは薄々感じていたとしても、彼女の雇い主が配置換えをしようとしないので、そのままになっているか。よくわからないが、だって大体、俺じゃあるまいし、あんなバラバラのコーナーで、あんなに熱心に立ち読みをしているなんて、どんな読書傾向なんだよ。あり得ないでしょう。そう思うと私は、ますます愉快痛快な気分になって、彼女の正体を自分が暴いたら、どうなるのだろうと考えて心中嬉々とした。これは、もう、ほんとにやってみるしかあるまい。
ある日のことである。私はやはり同じ店の片隅で、彼女を見つけた。いつものように静かに頁を捲って、淡々と立ち読みをしている。すでに二人の距離は数メートルしかない。私はゆっくりと近づいた。そして前から用意していた言葉を、なにげなさを装いつつ、声に出して彼女に告げた。相手の驚く顔を期待して、思わず少しにやにやしていたかもしれない。
「お疲れ様です」
すると彼女は顔を上げて、持っていた本を閉じた。見れば見るほど地味な顔立ちだ。一度会ったくらいではすぐに忘れてしまいそうな、何度会ってもほとんど記憶に残らないような、何の特徴も表情も魅力もない顔。彼女は、私をまっすぐに見た。そして、これまで一度も見たことのないような奇妙な笑みを浮かべて、こう言った。
「やっと気づいてくれましたね」
私は、戦慄した。
*******
ほどなく彼等がステージに登場し、演奏が始まった。なぜかギターのY君が居ない。この演目のタイトルには憶えがあった。何年か前に、同じ会場であった或るイベントに彼等が出演した際に披露された「演奏中に『お気づきだっただろうか?』という字幕とナレーションが挿入され、そのたびに同じ曲が何度も繰り返され、やがてスローモーション。スーパースローモーションと反復するにつれて、最初は見えていなかったものが現れてくる」という小品の、これは拡大ヴァージョンであるようだった。複雑な屈折を有したハードコアサウンドが、リピートを続けながら思いも寄らない変異を遂げてゆく。それはスリリング、かつストレンジな体験であった。むろん元ネタはいわゆる「心霊ビデオ」の類いなのだが、それを生演奏でやるというのがミソである。そこに否応無しに宿る汗が飛び散るようなフィジカルさ、無意味なように見えて意味性に満ちたドラマツルギー、生真面目な不真面目さと不真面目な生真面目さ、それらすべてが、いかにも彼等らしい。何より音楽自体が格好良いのが良い。
だが私は、実のところ、それどころではなかったのだ。何故なら、気づいてしまったからである。激しくパフォーマンスする彼等の勇姿の向こう側、ステージの反対の客席の中に、あろうことか、彼女の姿を発見してしまったのだ。彼女は、あのときとまったく同じ奇妙な、いや、不気味な笑みを浮かべて、まっすぐにこちらを、私の方を見つめていた。バンドには目もくれていなかった。静かに笑いながら、微動だにせず、私をじっと見ていた。
私は、椅子を蹴るように立ち上がると、会場を慌てて出た。彼等に申し訳ないとは思ったが、もうそれどころではなかった。演奏は続いていた。お気づきだっただろうか?、という声が聞こえた。やっと気づいてくれましたね、という声が聞こえた。私は夜の六本木を走った。彼女が追ってくる気がした。頭がおかしくなりそうだった。私は、気づいてしまったのだ。だからもうおしまいだ。どうしてY田君は居なかったのだろう。あれからどうなったのだろう。私はこれからどうなってしまうのだろう。私は、振り返りもせず、ただ走った。
だから私は、作品評を書くには不適任なのである。この文章をもって、お詫びとしたい。
(この批評はフィクションです。もちろん私は公演を最後まで鑑賞しましたし、Y田君こと吉田君が登場してからの鬼気迫る奇奇怪怪の展開も堪能しました)
佐々木敦
1964年生まれ。批評家。音楽レーベルHEADZ主宰。早稲田大学文学学術院教授。著書に『小説家の饒舌』(メディア総合研究所)、『「批評」とは何か?』(メディア総合研究所)、『即興の解体/懐胎』(青土社)、『未知との遭遇』(筑摩書房)、『批評時空間』(新潮社)、『シチュエーションズ 「以後」をめぐって』(文藝春秋)などがある。
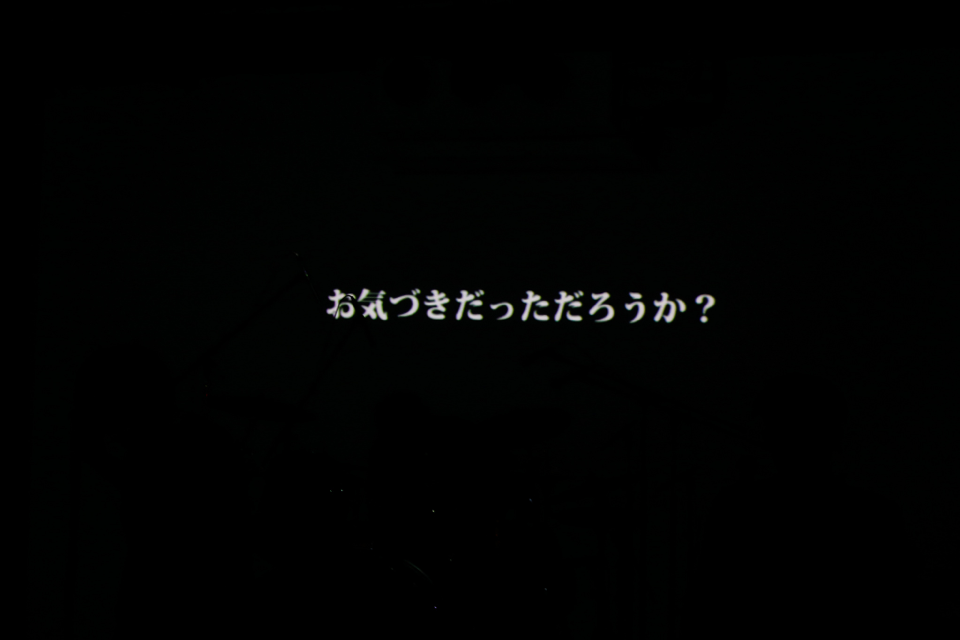
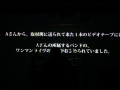






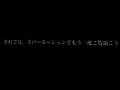


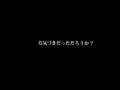










コメント