写真:前澤秀登
『怪物さんと退屈くんの12ヵ月』第二回公演
「moshing maniac 2000」
畠中実
会場には緑色のネットに囲われた立方体状の空間がある。
パイプによって枠を組まれた、いかにも仮設といった趣のそれは「檻」とでも言った方がしっくりくるだろう。客席の椅子の並べ方、観客の座っている方向によって、それは観客が観るべき方向、すなわちステージに位置していることがわかる。それはさほど大きくはないが、会場の天井いっぱいに、幅もほぼ客席から見れば視界いっぱいに広がっている。脇に中に入るための小さな入り口があり、その前には棍棒を持ったマッシュルームカットの赤鬼がいる。その「檻」の前方、会場の奥にバンドが演奏すると思われるステージがあることが、ドラム・セットやアンプなどが置いてあることからわかる。つまり、演奏が行なわれるステージは、その「檻」越しに見える位置にある。正確にはどちらもステージ、すなわち舞台に相当する場所にセットされたものである。会場であるスーパーデラックスの空間の大きさから考えて、バンドの演奏すると考えられるエリアは極めて狭いと思われる。くりかえせば、そのエリアと観客のいるフロアの間に先の「檻」が視界いっぱいに設置されている。つまり、テージは極めて見にくい。さらにはフロアの壁にはTwitterのタイムラインがプロジェクターで投影されている。ハッシュタグが設定されているらしい「#mm2000」。ここには開演前から会場の観客による実況がすでに呟かれており、ライヴ中も逐次会場の様子が伝えられるものと思われる。
これがとりあえずの会場の状態である。
開演前、フロアはいかにもcore of bells(以下COB)のファンといった風情の黒いTシャツを着た若い男女たちであふれていた。それは二重になったフロアだった。大人しく演奏を観ていたい観客は客席後ろで椅子に座っていればよい。より盛り上がりたい向きは、先の「檻」の中に入り、大勢で思い切り体をぶつけあい、汗をかき、モッシュに興じればよい、というわけだ。赤鬼もいるし、私はもちろん客席の後方からステージを見ることにする。そうするうちにフロント・アクトのNEVER END RAINBOWの演奏が始まる。個人的にはヴォーカリストのMCなど、好感度が高く気に入ったが、客席はほとんど盛り上がっていない。本人たちのひたむきさに比べ、残念だが客席の熱量はかなり低いと言わざるを得ない。「檻」の中もガラガラだ。ゆえに、演奏は「檻」の向こうにたしかに確認することができる。そこでは演奏が、たしかに、行なわれている。「檻」の向こうには確実に演奏のためのステージがある。観客も前座の演奏を聞き流すようにして、Twitterに呟いたりしながら、メイン・アクトを待っているようだ。すると、先ほどまでまわりにいたはずの大勢の黒Tシャツの若者たちが、潮が引くようにいなくなり、「檻」の中へとひとりふたりと入って行くではないか。みるみるそこは黒Tシャツの若者たちの充満した、高密度の空間となった。しかも「檻」は、フロアよりやや床があがっているため、人の塊に遮られてステージを観ることもままならない。
見えるのは、ただ「檻」の中の人の塊だ。
実際には、それは二重になったステージだった。正確にはまさに先の「檻」こそが観客が観るべきステージであった。公演タイトルからもなんとなく予測できるように(とはいえ、なぜ2000なのかはよくわからない)、観客のモッシュこそが当のパフォーマンスである、という作品なのだ。通常、観客とみなされる者たちは、ステージで繰り広げられるバンドなりの演奏に対して、音楽に合わせて体を動かし、つまり「ノって」みせることでミュージシャンへのシンパシーを表明し、一体感を感得する。そこにはあくまでも主としての、ステージ上に君臨するミュージシャンがいて、そして従としての観客という存在がある。その状況をさらに引いた視点でながめてみれば、ミュージシャンと観客との一体感、ステージと客席とが一体となった熱いステージといった状況をより客観的に見る観客がいる。それは、音楽に合わせ体を激しく動かし、ぶつけあい、ある者はジャンプし、観客の中にダイブする、モッシュ・ピット(モッシュの生起する場所)の状況を観察する観客だ。すなわち、この作品は、ライヴ会場におけるステージと観客とさらにもうひとつの観客という、ライヴにおける、ある状況を共有していながら、観客がステージ上にあがったり、逆にミュージシャンが観客の中にダイブするようなこともままあるにせよ、基本的にはそれぞれが相互に介入することのない三つの層を明確に分離することによって構造化したものだと言えよう。不可侵のステージ上のミュージシャン、思いのままにエネルギーを発散する観客との間には見えない「第四の壁」がある。というよりは、「第四の壁」に、4つの壁に囲われた観客が直面させられている。さらにそれらの状況を遠巻きに俯瞰するさらなる観客。
そうして構造化されたライヴにおける状況の、それぞれの部分の関係を入れ替えてしまったらどうなるか。
観客は、通常「観られる」ということを意識することはあまりないだろう。なぜなら、「観る/観られる」べきはステージ上のミュージシャンなのだから。もちろん、そうした中にもダイブというある種の自己顕示行為と看做されるものもあるにせよ、自分自身が楽しむという目的を誰に見せるためにでもなく、ただ遂行しているにすぎない。しかし、それを振付と看做したらどうなるか。それはCOBの『怪物さんと退屈くんの12ヵ月』ウェブサイトに掲載された紹介文に書かれていることが契機となっているだろう。モッシュという行為について、彼らがライヴに行った際の体験が語られている。それは、本来の目的であるべき目当てのバンドではなく、「ステージを取り囲む人々の群れに心を奪われた」ことが契機となっている。「最初はただデタラメに暴れているだけなのかとしばらく様子を見ていると、群衆は曲の展開に合わせて、フォーメーションや踊り方を細かく変えていることが分かって来ました」という。ように、それは単に観客各自のノリ方から、徐々になにか構成のようなものが暗黙のうちに形成されてくるのか、演目に合わせた段取り、振付のようなものが存在するということのようだ。そして今回、コンテンポラリー・モッシャーでもある危口統之が制作に関わり、モッシュを振り付けとして、ダンス/パフォーマンスを構成することにした。公演に参加したモッシュ・パフォーマーたちは、公演に先立ち、危口を講師に招いたワークショップ『core of bellsのコンテンポラリーモッシュ講座!〜moshing frontier 2000〜』に参加し、事前に練習を行ない、観客を演ずるパフォーマンスという転倒を行なってみせたのだ。先のワークショップの紹介文には、モッシュにみられる特徴として「(1)開演とともにコール(バンド名)を始める(2)代表曲が始まるとエキストラ同士が抱き合いガッツポーズをして歓喜する(3)エキストラ同士で支え合ったり、落ちた人をすぐ抱き起こしたりなど協力的である」などがあるとされる。公演ではそれらが、どこか戯画的に演じられ、いわば再構成されたモッシュ・ピットが現出していた。
それはたしかにダンス、パフォーマンスのようであった。
さりながら、しかし、観客はモッシュする(観客パフォーマーの演ずる)観客をただながめているというようにも見える。そして、パフォーマンスとしてのモッシュ、パフォーマンス化されたモッシュを観ているということを徐々に理解しながらも、どこか欲求不満のようなものが頭をもたげてくるのを感じる。それは、これはCOBのイヴェントではなかったか、ということである。今回は先の危口の参加により、ある種演劇的な(もちろん、COBにまさか所謂コンサートを期待しているわけではないにしても)意匠がほどこされ、それが前面に出ていると思ってみても、ここにはCOB自体の不在が存在感を増してくる。たしかに、今回の公演においてCOBは、あくまでもパフォーマンスの音楽を担当するバンドにすぎないとも言える。演劇的なシチュエーションだと考えれば、黒Tシャツの若者が充満した「檻」でさえ、仮構のライヴ会場なのであり、そこに鳴り響くのは生演奏である必要もない。意図的にか、COBの演奏のライヴ感のなさ、MCの棒読み感には、それが如実に現れていたように思う。
そこには観られる必要のない、観られることから解放されたバンドの姿が(見えないにしろ)あった。なにしろ、舞台と客席は逆転されているのだから。
演奏者が現れないライヴというものは、通常ロック・コンサートなどではありえない。
なぜなら、ライヴであるということは、あるミュージシャンによって目の前で実際に演奏されている、ということが重要だからだ。かつてジョン・ライドン率いるパブリック・イメージ・リミテッド(以下PIL)が、1981年にニューヨークのクラブ、リッツで行なった悪名高い暴動ライヴがを思い出す向きもあるだろう。PILはバウ・ワウ・ワウの代わりに急遽演奏することになり、リハーサルもなんの準備もないままに会場に到着した。会場にはスクリーンとプロジェクターがあったため、PILはヴィデオを上映し、スクリーンの後ろで演奏をすることにした。そんなことをまったく知らぬ観客は、その日自分たちのヒーローを観るために何時間も待たされていたという。会場にはまさに開演を待ちきれぬ「PIL、PIL、PIL」のコールが沸き起こっていた。しかし、始まったのPILの弛緩した演奏と、ライドンによる観客をバカにするようなMCだった……、しかもメンバーはスクリーンの後ろにいて姿も見えない。そして激昂した観客がスクリーンを引きちぎりステージに押し寄せる暴動の有様となり、PILのメンバーは会場から命からがら逃げ切ったという。それは、PILのヴィデオ・パフォーマンスだった。今回の公演も同様、COBの姿を観ることはできず、観客の前にはスクリーン(遮蔽幕)のごとき人の塊がある。
Twitterによる実況が映し出されるスクリーンによって、その状況を確認することしかできない。
とはいえ、その実況たるや、どうみても仕込みのやらせのようである。たまに会場の観客からの参加もあったように思うが、全体としては虚構のライヴが捏造されているといった趣である。たしかに、フロント・アクトを擁し、そうした演劇的な周到さによって、ライヴの情景というものが醸し出されていたと言っていいだろう。しかし、このなにかを目撃していながら、それが実際にはなにを観ているのか/見せられているのかがわからないという感覚。たとえば、突然差し挟まれた無音は一体なんだったのか。その時、演奏のステージでは何が起こっていたのかまったくわからない。すべてを想像力によって補うしかない。ライヴはただ進行するが、なにかが、確実に欠けている。
そして唐突に、ミケランジェロ・アントニオーニの映画『欲望(Blow Up)』(1966)を思い出す。
映画の終盤、主人公が迷い込むようにして入ったライヴハウスでは、バンド(ヤードバーズ)の演奏が繰り広げられていた。演奏中、アンプの調子が悪いことに苛立つリード・ギタリスト(ジェフ・ベック)がアンプをギターで叩き始める。やがてそれはエスカレートし、ギターのネックは折れ、ボディは踏みつけられ、破壊される。ギタリストが破壊されたギターのネックを客席に放り投げると、観客は押し合いへし合いしながらそれを奪い合う。主人公はなんとかギターの残骸を手にすることができた。それでも、追いかけて来る観客を振り切ってライヴハウスの外に出る。ふと熱狂から醒めて我に帰れば、自分が手にしているものはただのガラクタでしかなく、主人公は、くだらないものとでも言うようにそれを投げ捨てる。どこにもたしかな現実などというものはなく、確実な価値などというものもない。世界という不確かなものを引き延ばし、拡大すればするほど、そのたしからしさは失われていく。
公演の最後に、モッシュを演じていた若者たちが大挙して「檻」から溢れ出てくるさまは、どこか『欲望』の1シーンを思い出させた。
そして、残されたのは、からっぽのステージであった。
私が観ていたのは、映画『欲望』のラストに登場する、ボールのないテニスに興じる一団のようなものだったのかもしれない。演奏者と観客との関係が曖昧な、あるいは分断されているようにもみえるパフォーマンス。そこには、不在のCOBの音楽が、どこからか私の耳に聴こえていたのかもしれない。
畠中実
1968年生まれ。1996年の開館準備よりICCに携わる。主な企画には「サウンド・アート―音というメディア」(2000年)、「サウンディング・スペース」(2003年)、「サイレント・ダイアローグ」(2007年)、「可能世界空間論」(2010年)、「みえないちから」(2010年)、「[インターネット アート これから]—ポスト・インターネットのリアリティ」(2012年)など。ダムタイプ、明和電機、ローリー・アンダーソン、八谷和彦、磯崎新といった作家の個展企画も行なっている。





















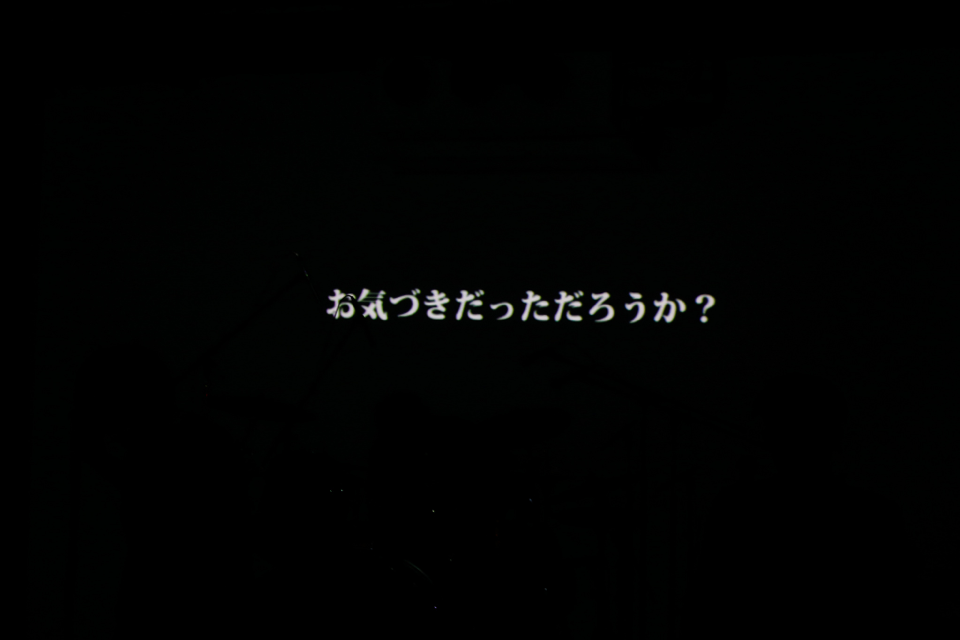

コメント